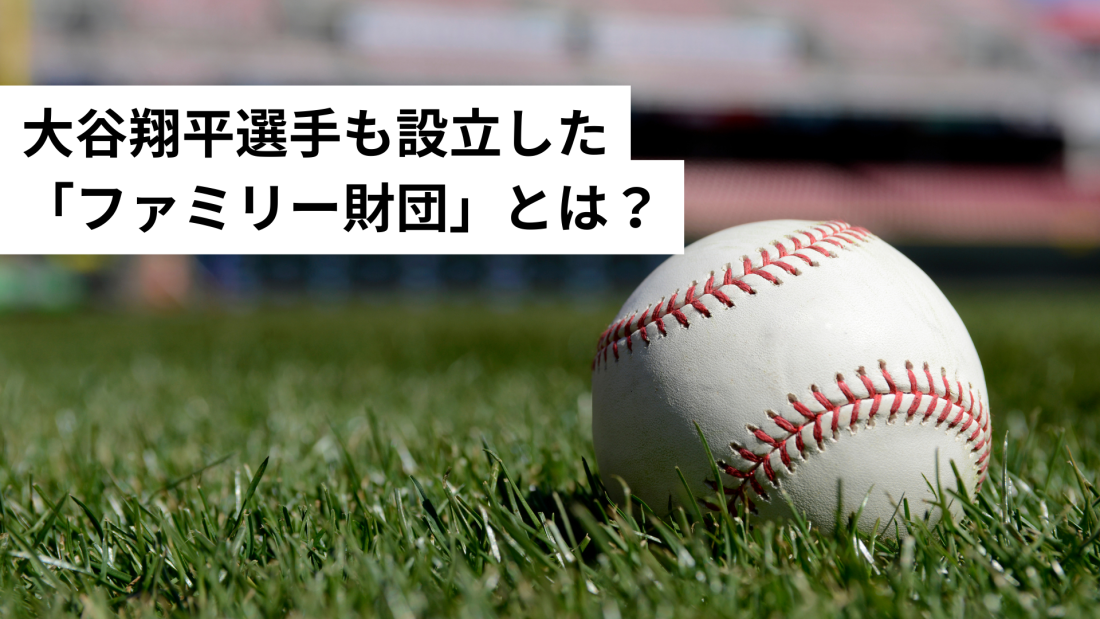
大谷翔平選手も設立した「ファミリー財団」とは?─日米の数字が語る、次世代へ想いを遺す「仕組み」の文化
2025.12.05
執筆:樽本 哲(インテアス法律事務所)
先日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が、自身の名を冠したSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION(大谷翔平ファミリー財団)の設立を発表しました。ロゴには家族3人と愛犬のデコピンくんが未来に向かって歩みを進める姿が描かれ、慈善活動への強い想いをうかがうことができます。
一見すると、スター選手の社会貢献活動として語られがちですが、この「ファミリー財団」という存在には、米国社会に深く根付く一つの文化が凝縮されています。それは、「次世代への使命(Generativity)」を、法的な仕組みを使って形にするという文化です。
大谷選手が設立した財団はどのような存在なのか。その実態と、内閣府の調査などから見える日本の現状とを比較しつつ、掘り下げてみたいと思います。
1 数字で見る米国の「寄付インフラ」
ファミリー財団とは、富裕な個人や家族が私財を投じて設立する民間の非営利団体のことです。日本ではまだ馴染みの薄い言葉ですが、米国では驚くべき規模で普及しています。
米国歳入庁(IRS)などのデータによると、米国にはチャリティや教育を目的とする非営利団体(501(c)(3)団体)が約150万団体も存在します。そして、その中で、主に特定の個人や家族が出した資金で運営される「私立財団(Private Foundation)」は、2021年時点で130,444団体に上ります(出典:内閣府委託調査「令和5年度 公益法人制度の見直しに向けた調査業務報告書」より)。この「私立財団」の大部分を「ファミリー財団」が占めていると言われています。
つまり、大谷選手の財団設立は特異な行動ではなく、米国の13万もの家族が実践している「成功者のスタンダード」なのです。彼らの多くは、慈善活動を通じて社会的な影響力を広げ、自分たちの理念を次世代に継承していくことを目指しています。
2 なぜ「ファミリー財団」なのか? ──Generativityの器として
なぜ、これほど多くの人々が、単に寄付をするだけでなく、わざわざ「財団」を設立するのでしょうか。
その最大の理由は、ファミリー財団が、設立者のGenerativity(世代継承性)を実現するための強力な「法的な器」だからです。
実例:ロックフェラーからパタゴニアまで──「仕組み」で想いを遺す人々
米国では、歴史的な財閥から現代の起業家まで、成功者の多くがこの「仕組み」を活用しています。
世界最大のファミリー財団として、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が資産の大部分を移転。医療や貧困対策に巨額の資金を投じ、「世界を良くする」というミッションを家族の共通言語にしています。
100年以上前に石油王ジョン・D・ロックフェラーが設立。一族は代々フィランソロピーに関わり続け、富める者の社会的責任という米国の寄付文化の礎を築きました。
アウトドアブランド「パタゴニア」の創業者イヴォン・シュイナード氏は、2022年に会社そのものを譲渡。利益が永久に環境保護のために使われるよう、法律(信託と非営利法人)を駆使して「理念の永続化」を設計した、Generativityの究極形と言えるでしょう。
Generativityの器としての機能
財団は、設立者が築いた富や影響力を、一過性の消費で終わらせず、「次世代への貢献」という形で恒久的な仕組みに変えます。大谷選手が支援対象を「子ども」や「動物」と定めたように、自身の関心を長期的なミッションとして社会に定着させることができます。
「ファミリー」の名が示す通り、家族が運営に関わることで、慈善活動を通じて共通の価値観や理念を共有します。財団は、資産だけでなく、「私たちは社会に対してどうあるべきか」という精神的支柱(ファミリー・アイデンティティ)を次世代へ継承する役割を担うのです。
ファミリー財団は、設立者に対して大きな税制上のインセンティブを提供します。
私立財団には、他の団体に資金援助を行う「助成型」と、自ら慈善事業を直接行う「事業型」があり、その活動内容によって優遇措置の度合いは異なりますが、いずれもメリットは明白です。
具体的には、自らが設立したファミリー財団へ現金を寄付した場合、寄付者は調整後総所得(AGI)の30%を上限(助成型財団の場合)として所得税の控除を受けることができます。さらに、評価額が上がった不動産や株式などの資産を寄付した場合、その譲渡益(キャピタルゲイン)が非課税となるメリットがあります。資産を売却することなく、時価のまま全額を財団へ移転できるため、実質的な節税効果は非常に大きいと言えます(上記報告書より)。
一方で、財団自体は原則として連邦所得税が免除されますが、資産運用による収益に対しては財団の資産規模に応じて1.39%から最大10%のエグザイズ税(投資収益税)が課税される※など、厳格なルールが伴います。
※トランプ政権下で2025年7月に成立した「One Big Beautiful Bill Act」により、従来のフラット税率から階層別税率(小規模は1.39%、超大規模は10%)へと変更されました。
この厳しいルールの最たるものが「5%ペイアウトルール」です。財団は、毎年、前年度の資産残高の5%以上を、助成金や公益目的の事業のために支出しなければなりません。これは、財団が単なる節税や資産隠しの道具になることを防ぎ、確実に富が社会へ還流されることを担保する仕組みです。
4 内閣府の調査が示唆する「日本の課題」
一方、日本の現状はどうでしょうか。内閣府が実施した「諸外国における公益法人制度等に関する調査」(令和5年度報告書など)では、日米の制度の決定的な違いが浮き彫りになっています。調査が示唆するのは、「入り口の広さ」と「事後監視」の違いです。
米国:入り口は広く、出口(監視)は厳しく
米国では、法人の設立や免税資格の取得は比較的容易(入り口が広い)ですが、その分、IRSによる情報開示要求や、前述のペイアウトルール、自己取引の禁止といった事後的な監視・規律が非常に厳格です。この「規律ある自由」が、13万件もの財団活動を支えています。
日本:入り口が狭いが、改革により「変化」の兆しも
対して日本は、長らく「公益認定」のハードルが高く、資産家や経営者が自分の想いを柔軟に実現するための「器」を容易には作れない時代が続いてきました。内閣府の報告書でも、この制度的課題が分析されています。
しかし、日本でも変化が起きています。令和6年(2024年)5月、公益法人制度の改革関連法が成立しました。 この改革では、財務規律の柔軟化や行政手続きの簡素化などが盛り込まれ、より運営しやすく、多様な公益活動を支える制度へと舵が切られました。さらに、公益信託制度についても、担い手の範囲の拡大、信託財産・信託事務の範囲拡大、認可・監督基準の統一など、利用促進に向けた改革が進められており、多様な「想いの受け皿」を整備しようという国としての意思表示が明確になっています。
おわりに:日本に「想いのインフラ」を育てるために
大谷選手が示したように、「自分の想いと価値観を、仕組みによって未来に永続させる」という行為は、人間が持つ本質的な願い(Generativity)です。
米国のファミリー財団のようなダイナミックな寄付文化が日本にも根付くのか。それは、今回の公益法人改革や公益信託の利用促進に向けた制度改正が、現場でどのように運用され、実を結んでいくかにかかっています。
その成果を注視しながら、私も弁護士として、想いを託そうとする人々の「庭」づくりを支え続けていきたいと思います。

